退職を申し出たところ、上司から「勝手に辞めるなら解雇だ」と言われた――そんな経験をされた方も少なくありません。これは一見すると脅しのようであり、また本当に解雇されてしまうのではないかと不安に感じる方もいるでしょう。しかし、退職と解雇はまったく性質の異なる労働契約の終了手段であり、退職を申し出たからといって「解雇」されるのは本来、法律的に不適切です。
労働者には退職の自由があります。これは憲法上も認められた権利であり、民法にも定められている明確なルールです。一方で、会社が労働者を解雇するためには、客観的かつ合理的な理由が必要であり、社会通念上相当でなければ不当解雇とされる可能性があります。
本記事では、「退職したいのに『解雇する』と脅されている」ようなケースにおいて、何が合法で、何が不当なのか、実際にどんな対応を取るべきかを法律的観点から詳しく解説します。労働者として自分の権利を守るために、正確な知識を持って冷静に対応することが大切です。
退職意思に対して「解雇」とはどういうことか?
退職の申し入れは労働者の当然の権利です。それにもかかわらず、退職の意志を伝えた際に「そんなことを言うなら解雇にする」と返されることがあります。これは一種の脅しや感情的な発言であることもありますが、まず確認したいのは、退職と解雇の意味の違いです。
「退職」は本人の意思で労働契約を終了するものであり、「解雇」は会社が一方的に労働契約を終了するものです。つまり、両者の主導権が異なります。
会社が「解雇する」と言ってきた場合、それは本当に解雇としての手続きを取るのか、単に脅しとして言っているのかを見極める必要があります。
「辞めるなら解雇だ」は法的に許される?
会社が従業員の退職意思に対して「それなら解雇だ」と対応するのは、法的に非常に問題があります。なぜなら、日本の労働法では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされており、それがない解雇は「解雇権の濫用」として無効になるからです(労働契約法第16条)。
退職の意思表示をしたという理由で解雇するのは、合理的理由に該当しません。また、労働者に不利益を与える目的で解雇をちらつかせるのは、パワハラ(パワーハラスメント)とみなされる可能性もあります。
解雇と伝えられた場合、従業員はどう対応すべきか
万が一、会社から「明日から来なくていい」「解雇だ」と言われた場合には、まず冷静に対応することが重要です。可能な限り以下のことを行いましょう:
- 解雇の理由を明確に確認する
- 解雇通知書など、書面での通知を求める
- 会話の内容を録音する、あるいはメモを取る
特に「解雇通知書」を求めることで、会社側の法的根拠の有無を確認することができます。これが出てこない場合、単なる口頭での脅しに過ぎない可能性が高くなります。
解雇予告と解雇予告手当の基本知識
法律上、会社が従業員を解雇する場合、原則として30日前の解雇予告が必要です。これを行わない場合には、30日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要があります(労働基準法第20条)。
このため、突然「今日でクビだ」と言われた場合でも、即日の解雇が無効になる可能性があります。また、解雇理由があいまいなままで、予告手当の支払いもないといった場合は、明確に違法性を主張できる材料となります。
「懲戒解雇にするぞ」は脅し文句?その真偽と対処法
退職の申し出をした際に「そんなことをするなら懲戒解雇にする」と言われたら、さらに注意が必要です。懲戒解雇とは、就業規則違反や重大な背任行為などがあった場合に認められる最も重い処分であり、これにも厳しい条件が課されます。
一般的に、退職意思を示しただけで懲戒解雇が認められることはありません。仮に懲戒解雇処分がされた場合でも、それに不服があれば労働審判や裁判などで争うことが可能です。
会社側が懲戒解雇をちらつかせてくるような場合は、すぐに証拠を記録し、労働組合や労働局、弁護士などの専門家に相談しましょう。
退職を申し出た後にすべき3つの行動
退職を申し出た際に会社と揉めそうな場合は、次のような対策を講じることが大切です。
- 退職の意思は書面で残す メールや退職届など、証拠に残る形で意思表示しましょう。
- 会話は録音、やり取りは記録する 不当な発言や脅しがあった場合に備えて記録を取りましょう。
- 第三者機関に早めに相談する 早めに外部のサポートを受けることで、心理的にも法的にも安心できます。
不当な解雇・脅しに直面したときの相談先と救済手段
不当解雇や脅しに直面した場合は、以下のような窓口があります。
- 労働基準監督署:労働基準法に基づく対応をしてくれる公的機関
- 労働組合(ユニオン):交渉の代行を行ってくれることも
- 法テラス:無料で弁護士相談を受けることができる窓口
- 弁護士:不当解雇の損害賠償請求や地位確認請求などに対応
- 退職代行サービス:本人に代わって意思表示や会社との連絡を行う
精神的なダメージが大きいときは、自分だけで抱え込まずに、信頼できる第三者に相談することが何よりも大切です。
まとめ
退職の申し出をした際に、会社側から「解雇する」と脅されるようなケースは、法律上問題のある対応です。労働者には退職の自由があり、これは民法にも明確に定められている基本的な権利です。一方で、会社が労働者を解雇するためには、客観的に合理的な理由が必要であり、それがなければ不当解雇として無効とされることがあります。
「退職を申し出たから解雇」といった理由は、通常、解雇の正当な理由には該当しません。これは裁判でも繰り返し否定されており、仮に解雇されたとしても、法的手段により争うことが可能です。こうしたトラブルを避けるためには、退職の意思表示を文書やメールで記録に残し、冷静かつ客観的な対応を心がけることが重要です。
万が一、脅しや不当な対応が続くようであれば、労働基準監督署や法テラス、ユニオン、弁護士など、外部の相談機関を活用することも視野に入れましょう。泣き寝入りせず、正当な権利を主張する姿勢が、自身を守ることにつながります。
| 項目 | 内容 |
| 労働者の権利 | 退職は労働者の自由(民法627条)であり、2週間前の申し出で雇用契約は終了できます。 |
| 会社の対応 | 「退職したいなら解雇する」といった発言は、不当な脅しに該当する可能性があります。 |
| 解雇の条件 | 解雇は客観的合理性と社会的相当性がなければ無効(労働契約法第16条)です。 |
| 対応の仕方 | 記録を残す(メール・書面)、冷静に対応、感情的にならないことが大切。 |
| 相談機関 | 労基署、法テラス、ユニオン、弁護士、退職代行などの利用も検討しましょう。 |
🔎 チェックリスト:あなたの対応は万全ですか?
- 退職の意思を文書またはメールで伝えた
- 上司の発言を録音・メモで記録している
- 引継ぎ対応をある程度進めている
- 不当な扱いを受けた場合の相談先を調べている
- 必要であれば第三者機関の利用も検討している
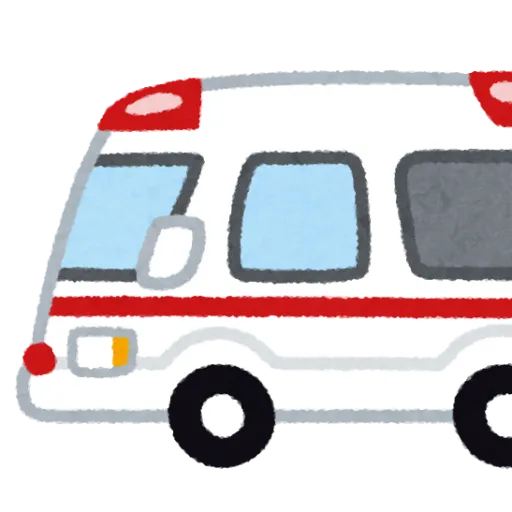
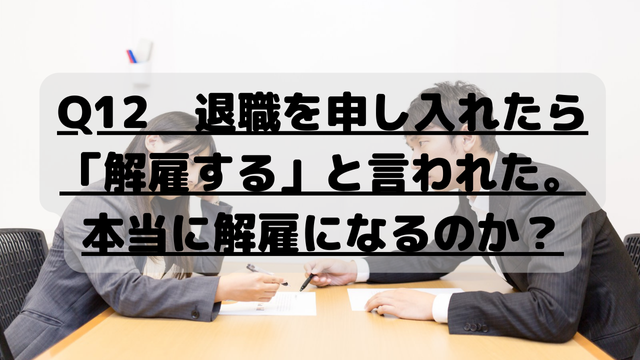
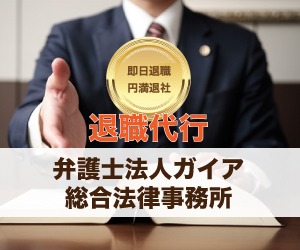
コメント