「長年勤めた会社を退職する。新しい生活が始まるのは楽しみだけど、税金の手続きってどうなるんだろう?」
退職は、生活環境だけでなく、税金の手続きにも大きな変化が生じるタイミングです。退職金を受け取った場合、在職中に支払っていた所得税や住民税の扱い、そして場合によっては確定申告が必要になることもあります。
税金に関する知識がないまま退職を迎えてしまうと、思わぬ納税額が発生したり、本来受けられるはずの控除を受けられなかったりする可能性があります。
この記事では、退職金にかかる税金、退職年の所得税と住民税、確定申告の必要性、そして再就職した場合の税金の扱いについて詳しく解説していきます。退職前に税金の知識をしっかりと身につけ、スムーズに新しい生活をスタートさせましょう。
退職金にかかる税金!計算方法と控除の種類
長年勤めた会社から支払われる退職金は、所得税と住民税の課税対象となります。しかし、退職金は一時的な所得であり、長年の勤労に対する報奨的な意味合いも持つため、税負担が軽減されるように「退職所得控除」という特別な控除が設けられています。
退職所得の計算方法:
退職金の税額を計算する際の課税対象となるのは、退職金そのものの金額ではなく、「退職所得」と呼ばれる金額です。退職所得は、以下の計算式で算出されます。
退職所得=(退職金の額−退職所得控除額)×0.5
このように、退職金から退職所得控除額を差し引いた金額のさらに2分の1が課税対象となるため、税負担が大きく軽減される仕組みになっています。
退職所得控除額:
退職所得控除額は、勤続年数に応じて以下のように計算されます。
- 勤続年数20年以下の場合:40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続年数20年超の場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
例えば、勤続年数10年で退職金が500万円だった場合、退職所得控除額は40万円 × 10年 = 400万円となり、退職所得は (500万円 – 400万円) × 1/2 = 50万円となります。
また、勤続年数30年で退職金が2000万円だった場合、退職所得控除額は 800万円 + 70万円 × (30年 – 20年) = 1500万円となり、退職所得は (2000万円 – 1500万円) × 1/2 = 250万円となります。
退職金の源泉徴収:
通常、退職金は支払われる際に所得税と住民税が源泉徴収されます。税額は、会社が上記の計算方法に基づいて算出し、差し引いて納税します。この源泉徴収によって、原則として退職金に関する所得税と住民税の納税は完了するため、確定申告は不要となることが多いです。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、一律20.42%の所得税が源泉徴収されるため、確定申告を行うことで過払い分の税金が還付される可能性があります。
退職所得控除とは?勤続年数で大きく変わる控除額
前述の通り、退職金には「退職所得控除」という特別な所得控除が適用されます。この控除額は、長年の勤労に対する報奨という退職金の性質を考慮して、勤続年数が長くなるほど大きくなるように設計されています。
勤続年数が控除額に与える影響:
- 勤続年数20年以下: 勤続年数1年あたり40万円の控除額が適用されます。最低控除額は80万円です。短期間の勤務の場合でも、一定の控除が保障されています。
- 勤続年数20年超: 勤続年数20年を超えると、控除額の計算方法が変わり、控除額の伸びが大きくなります。これは、長期間会社に貢献した従業員への配慮と言えるでしょう。20年を超える部分については、1年あたり70万円が加算されます。
控除額の重要性:
退職所得控除額が大きいほど、退職所得の金額が小さくなり、結果として課税される所得税と住民税の額も少なく抑えられます。したがって、退職金の税金を考える上で、自身の勤続年数を正確に把握し、退職所得控除額を計算することが非常に重要になります。
また、同じ年に複数の会社から退職金を受け取る場合は、勤続年数を合算して控除額を計算するのではなく、それぞれの退職金に対して個別に退職所得控除額を計算します。
源泉徴収票をチェック!退職所得の金額と税額
退職金が支払われた後、会社から「退職所得の源泉徴収票」が交付されます。この書類には、支払われた退職金の金額、退職所得控除額、退職所得の金額、源泉徴収された所得税額と住民税額などが記載されています。
源泉徴収票の確認ポイント:
- 退職金の金額: 実際に受け取った退職金の総額が記載されているか確認します。
- 退職所得控除額: 勤続年数に基づいて計算された控除額が記載されているか確認します。
- 退職所得の金額: 「(退職金の額 – 退職所得控除額)× 1/2」で計算された金額が記載されているか確認します。
- 源泉徴収額: 源泉徴収された所得税と住民税の金額が記載されています。
もし、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合は、この源泉徴収票に記載された税額で納税が完了しているため、原則として確定申告は不要です。
しかし、申告書を提出していない場合や、源泉徴収された税額に疑問がある場合は、確定申告を行うことで税金の過不足を精算することができます。源泉徴収票は、確定申告を行う際に必要となる重要な書類ですので、大切に保管しておきましょう。
年の途中で退職した場合の所得税と住民税
年の途中で退職した場合、在職中に支払っていた所得税と住民税の扱いは以下のようになります。
所得税:
在職中に毎月の給与から源泉徴収されていた所得税は、あくまで概算で計算されたものです。年の途中で退職した場合、その年の1月1日から退職日までの所得に基づいて、改めて正確な所得税額が計算され、過不足が精算されます。この精算は、通常、最後の給与や退職金の支払い時に行われます。
ただし、年の途中で再就職し、新しい会社で年末調整を受ける場合は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出することで、まとめて所得税の精算が行われます。
住民税:
住民税は、前年の所得に基づいて計算され、原則として6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きされます。年の途中で退職した場合、残りの住民税は以下のいずれかの方法で納付することになります。
- 最後の給与から一括徴収: 退職する時期によっては、残りの住民税が最後の給与から一括で徴収されることがあります。
- 普通徴収: 一括徴収されなかった場合は、市区町村から納付書が送られてくるため、自身で納付する必要があります。
退職後、住所が変わる場合は、速やかに市区町村に転居の手続きを行い、住民税の納付書が確実に届くようにしましょう。
確定申告は必要?退職所得以外の所得がある場合など
原則として、退職金にかかる所得税と住民税は源泉徴収によって納税が完了するため、確定申告は不要となることが多いです。しかし、以下のようなケースでは確定申告が必要になる場合があります。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合: この場合、退職金から一律20.42%の所得税が源泉徴収されているため、確定申告を行うことで過払い分の税金が還付される可能性があります。
- 退職所得以外の所得がある場合: 例えば、退職した年に不動産所得や副業による所得など、退職所得以外の所得がある場合は、それらの所得と合わせて確定申告を行う必要があります。
- 医療費控除や扶養控除などを受けたい場合: 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合で、医療費控除や扶養控除などを受けたい場合は、自身で確定申告を行う必要があります。
- 退職所得控除額に誤りがある場合: 源泉徴収票に記載されている退職所得控除額が、自身の勤続年数に基づいて正しく計算されていないと思われる場合は、確定申告を行うことで修正を求めることができます。
確定申告の期間は、通常、翌年の2月16日から3月15日までです。必要書類を準備し、税務署の窓口やe-Taxを利用して手続きを行いましょう。
再就職した場合の税金!年末調整はどうなる?
年の途中で退職し、その後すぐに新しい会社に再就職した場合、所得税の年末調整は新しい会社で行うことができます。
年末調整に必要な書類:
新しい会社で年末調整を受けるためには、以下の書類を提出する必要があります。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書: 新しい会社から渡される書類に、扶養親族などの情報を記入して提出します。
- 前の会社の源泉徴収票: 退職した会社から交付された源泉徴収票を、新しい会社に提出します。これにより、年間の所得と源泉徴収された所得税額が合算され、年末調整が行われます。
- 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書など: これらの控除を受けたい場合は、それぞれの控除証明書を新しい会社に提出します。
これらの書類を期限内に新しい会社に提出することで、年間の所得税の過不足が精算され、還付または追加徴収が行われます。
住民税の納付:
再就職した場合、退職した年の6月から翌年5月までの住民税は、新しい会社の給与から天引きされるのが一般的です。手続きについては、新しい会社の人事担当者に確認しましょう。
税金で損しないために!退職前に知っておくべきこと
退職後に税金で損をしないためには、退職前に以下の点を把握しておくことが重要です。
- 退職金の金額と勤続年数: 退職金の金額と自身の勤続年数を把握し、退職所得控除額の目安を計算しておきましょう。
- 「退職所得の受給に関する申告書」の提出: 可能であれば、退職金の支払いを受ける前に会社に提出しておきましょう。
- 源泉徴収票の保管: 退職所得の源泉徴収票と、退職した年の給与所得の源泉徴収票は、確定申告などで必要になる可能性があるため、大切に保管しておきましょう。
- 退職後の所得の見込み: 退職後にアルバイトや年金収入など、退職所得以外の所得が見込まれる場合は、確定申告が必要になる可能性があることを考慮しておきましょう。
- 税務署や税理士への相談: 税金に関する疑問や不安がある場合は、税務署の税務相談窓口や税理士に相談することを検討しましょう。
退職は新たなスタートを切るための大切な機会です。税金に関する知識をしっかりと身につけ、安心して次のステップに進めるように準備しましょう。
まとめ
今回の記事では、退職に関わる税金について、退職金、所得税、住民税を中心に詳しく解説しました。退職金の税金は退職所得控除によって軽減されますが、源泉徴収票の確認や確定申告の必要性など、注意すべき点もあります。また、年の途中で退職した場合の所得税と住民税の扱い、再就職した場合の年末調整についても理解しておくことが重要です。退職前にしっかりと税金の知識を身につけ、スムーズな移行を実現してください。
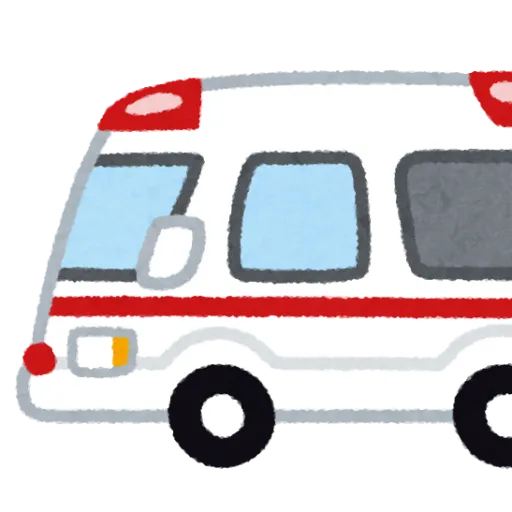
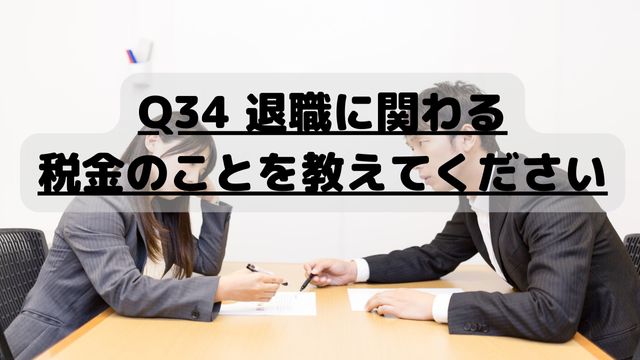
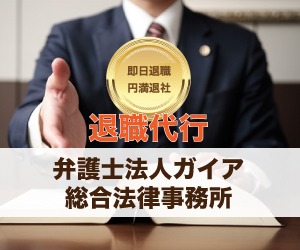
コメント